当サイトをご覧いただき
ありがとうございます♪
自分軸makingパートナーの
高橋かのんです。
(初めましての方は、こちらを)

あなたは、AED(自動体外式除細動器)に
触ったことがありますか?

おそらく多くの方が「NO」
ではないでしょうか。
たくさん設置されてきているのは
知っている
でも、いざというとき
ただでさえ気が動転しているのに
使える気がしない。
それが私の率直な思いでした。
というわけで
救命講習を受けてきました!
これ、全員、受けた方がいいです!!
私の体験レポです。
救命講習とは
救命講習とは
心肺停止や怪我など
救命、対処を必要とした方を発見した際に
どうしたらいいのか。
救命の方法を学ぶための講習です。
具体的には
心肺蘇生法やAEDの使い方
止血法や喉に何かを詰まらせた時の対処法など
テキストや動画
実際に体を動かして
学びます。
この実際に体を動かして学ぶが
この講習でしか学べないから
重要と思っています。
気が動転したときには
体で覚えたことの方が
動けると思うからです。
どこで受けられる?
全国各地で開催されています。
主催団体は2つ。
消防庁と赤十字です。
消防庁主催のものは、
東京であれば、東京消防庁↓
公益財団防災救急協会↓
赤十字主催の講習は、
にそれぞれ詳細が載っています。
講習の種類と料金
講習の種類は、
消防庁の場合
普通救命講習(3時間/¥1700)と上級救命講習(8時間/¥3400)
赤十字の場合
基礎講習(4時間/¥1500)と救急員養成講習(10時間/¥2100)
があります。
講習の内容
それぞれの講習で学ぶこと
違いはなんでしょうか。
普通救命講習と上級救命講習の違いは
普通救命講習では、成人の心肺蘇生法、自動体外式除細動器(AED)の使用法、気道異物除去法を、3時間で実施しています。上級救命講習では、普通救命講習の内容に加え小児・乳児の心肺蘇生法、外傷の手当て、保温法、体位管理法、搬送法を実施し、実技及び筆記試験を含め8時間で行っています。
朝加八潮消防組合HPより引用
赤十字の
基礎講習と救急員養成講習の違いは
基礎講習では、手当の基本、人工呼吸や胸骨圧迫の方法、AED(自動体外式除細動器)を用いた電気ショックなどを習得できます。
救急員養成講習では、日常生活における事故防止や止血の仕方、包帯の使い方、骨折などの場合の固定、搬送、災害時の心得などについての知識と技術を習得できます。赤十字HPより引用
ちなみに、私が受けたのは
消防庁の上級救命講習です。
9:00〜17:00となっていますが
5人一組で学ぶ場合だそうで
私が参加した時は、3人一組だったので
16:00で終了しました。
何人一組かは、当日
行ってからわかることと思います。
そして、普通講習を受けてから出ないと
上級は受けられないというわけではなく
内容が被っているので
いきなり上級でOKです。
私は、どうせなら一気に全部
と思って上級にしました。
消防庁主催と赤十字の講習の違いは
赤十字の方には参加したことがないので
わかりませんが
赤十字の講習内容として書いてある記述を見ると
それほど変わりはないように思います。
上級救命講習・参加レポ
場所は、体育館のような広いところで
椅子が3つずつ並んで置いてあり
その前に、実習用の人形やAED が
置いてありました。

その3人で一組として
実習していきます。
3人は、男女別で組まれています。
自分で実習できるのは
貴重な機会ですし
人がしているのを見るのも
とても勉強になりました。
上級は、
小児・乳児の対応があるわけですが
やってみると
乳児の対応が成人とは違い
一番大変でした。
配布されるものは
テキスト
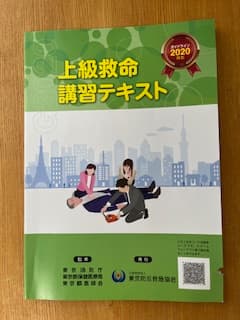
2020年版が最新とのこと。
それから、三角巾

人工呼吸を直接口をつけなくても
大丈夫にする器具です。
広げるとこんな感じ

これは実際に広げて
人形に設置しますが
口をつけて
実際に空気を送り込むことは
しません。
講習では、するふりだけです。
講習後、持ち帰り
常に何かあった時のために
持ち歩くことを推奨。
もし、使う場面に出会って
実際に使った場合には
新しいものを再度
もらえるそうです。
三角巾も実際に広げて
自分やペアの人(同姓)に
巻いてみる実習があります。
巻き方のコツとして
結び目は、内側にあると
ほつれるし痛いので
外側にするなど
ビジネスマナーと一緒で
相手を思いやれば
自然とできることも多く
一緒だなと思いました。
もちろん
思いやりではわからない知識の部分は
こうしたところで学ぶ必要が
ありますね。
認定証(テストは?)
以下の条件をクリアすると
・講習の全工程に参加
・講習中で行う実技実習が合格
・最後に行うテストに合格
最後に、救命技能認定証がいただけます。
紙の名刺サイズのものです。
実技も筆記テストも
落とすためのものではありません。
実技は、何グループかに一人
教えてくれる方がつくので
注意を受けながら
言われたことを練習していればOKです。
特に厳しくも言われません。
テストも
講習内でテキストを使っての講義の際
「ここテストに出ますよ、覚えてください」と
言われるので、注意してみておくだけでOKです。
テストは、講習が終わってすぐ行われ
丸バツの2択と3択問題で1問5点の100点満点
5分程度でできるものです。
その後、答え合わせを
各自でして回収。
何点以上が合格なども
言われず
間違ったところを
各自で、再度見ておくように
言われます。
よっぽど悪くなければ
大丈夫なのではないでしょうか。
ちなみに、認定証は
これがあるからといって
何かできるメリットはないと思います。
さらにその上の講習に行く場合は
必要なのかもしれませんが。
講習を終えて思うこと
これは、全員受けた方がいい!
と思いました。
ご家族や大切な人が
いつ、救命が必要な状態になるか
わからないですし
仕事中や街中で
出くわす可能性もあります。
そんな時
一度でも体を動かして
学ぶ機会を体験していたら
動ける可能性が高まると
思うのです。
誰だの命の恩人になれるかも^_−☆
また
そのような時に
気が動転して動けなかった
何もできなかった
となると
トラウマあるあるでは
罪悪感や無力感に苛まれることにも
なりかねません。
知っておいて
体験しておいて
損のない講習だと思います!
特に、ここでしかできない
実習できてよかったと思ったのは
以下のこと
・倒れたいる方を見つけた時の対応
これを流れで何度もできたので
実際もできるかもと思えてきましたし
やっておかなかったら
そもそも知らないし
こんな風には動けないと思いました。
・心肺蘇生
医療ドラマでよくみる
心臓を押すあれです。
あれをするときの手のイメージは
ありましたが、なぜあの形をするのかは
想像していたのと違いました。
健康な人にはできないので
人形を使っての練習はわかりやすかったです。
また、ペースや強さなども
知っておく必要があり
専用の機械でわかりやすく表示されたので
体感として習得しやすかったと思います。
ちなみに、この機械は
今の所、東京だと
本所の講習のみでついているそうです。
・AED
何のための装置かも
そもそも思い違えてました。
開いて、どうする?
付けるってどこに?
付けたら?使った後は?など
実際にやってみることは
こういう実習でないと
できないですよね。
ちなみに、講習は
トレーニング用のものだから
何度もつけたり剥がしたりできるように
してあるそう。
実際のものは
一度つけたら剥がせないように
なっていとのこと。
だったら、余計に
緊張して、初見ではなかなか
つけるのに勇気が入りそうです。
練習しておくにつきます!
というわけで、体験できる場所は
なかなかないですし
地震や津波、台風など
災害大国日本ですし
猛暑などでの熱中症も多くなってますし
この講習、全員におすすめです!!
時期にもよるのでしょうが
結構、人気で混んでいて
私は、2ヶ月後の講習で
申し込みできました。
お早めに、気長に
ご準備を^_−☆
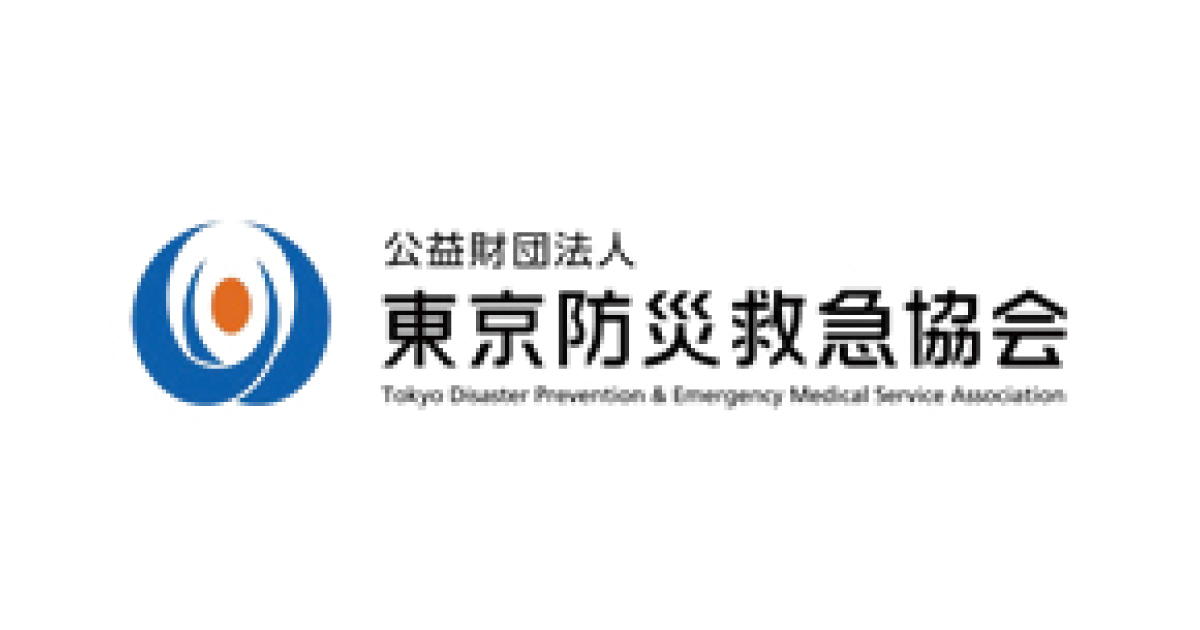









コメント